
もう5年以上前の話になりますが、
英語に耳を慣らすために、例文をi Podで聴いていたことがあります
あるとき、僕のi Podを見た外国人の知人に「それは何か?」と聞かれました
i Podを知らないのだと思い、説明をしたのですが、どうもポイントはそこではなかったらしい
つまり、スマートフォンを使って聴けばいいものを、なぜわざわざ別のデバイスを使うのか?
それが、質問の趣旨だったのでした
なぜ、そんな面倒なことをするのか?
i Podは小さく、使いやすいと思って、音楽とは分けて英語用として使っていたのですが、よく考えるとスマートフォンはいつも持ち歩いている
確かに、ふたつもデバイスを持ち歩く意味は何か。我に返り、それ以降i Podはあまり使わなくなってしまいました
別に、i Podが悪いと思っているわけではなく、例え話なのですが、なんでこんなことをやってるんだろうと、ふと思う瞬間はないでしょうか?
今日は、そんなことについて考えてみます

以前、中国の人々が、スマートフォンと街中に設置された監視カメラによって、行動をGPSで把握され、それがコロナ封じ込めにも使われているという話をしました
そんな中国の人々は、日本の家庭にあるような「固定電話」を知らないといいます
つまり経済成長により、固定電話が一般家庭に普及するよりも、携帯電話が先に行き渡ってしまった
日本人もよく知っていて、米中摩擦のある意味、象徴的存在ともなってしまった「華為」ファーウェイはじめ、「小米科技」シャオミや、「OPPO Electronics」オッポなど、中国には世界的にシェアを持つスマートフォンメーカーがあります
日本も、かつては電機メーカーが携帯電話で世界的にシェアを持っていた時代もあるのですが、かつて、例えば携帯電話の形状が複雑だったのが、スマートフォンに代わると、ものすごく単純な形状に変ったりとか、日本での製造コストが全く合わなくなってしまって、日本メーカーが撤退してしまったのですね
そんな、日本社会が順序を追って進歩してきたプロセスを、ひとつ飛びで自国の社会に取り込み、日本のレベルを追い越す
そういう事例が増えている気がしないでしょうか?
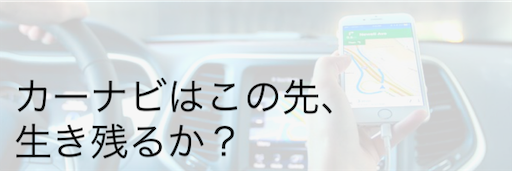
「ひとつ飛び」の事例は、実はかなりあったりする
例えば、なのですが、
カーナビ。海外でカーナビを装備している車は、日本と比べて断然に少ないです
ただし、みんなスマートフォンのカーナビアプリを使っているので、道路検索には不自由を感じていないでしょう
日本にいても、アプリだと、いつも最新の道路情報が反映されるので、だてに古いカーナビなんかよりも、はるかに使いやすかったりする
他にも、いろいろありそうです
そもそもカーナビ以前に、自動車産業が大きな転換期にいます
これまでトヨタ自動車や本田技研工業が優位性を誇ってきたガソリン車が、排ガス規制の問題を受け逆風にさらされています
ヨーロッパや中国、インドなどもそうなのですが、世界がEVへのシフトを明確に打ち出しています
今や、テスラの時価総額がトヨタのそれをはるかに上回る時代です
EVは、ガソリン車に比べて部品点数も少なく、いずれ早かれ遅かれ、日本のモノづくりメーカーの多くが、シビアな経営判断を迫られることになります
銀行のATMは、どうでしょうか
日本のATMは、現金の入出金だけではなく、通帳の記帳もできます。さらに、記入欄がいっぱいになった通帳を、繰り越しして、新しい通帳にしてくれたりします
海外の銀行にもATMはありますが、例えばCiti bank、シティバンクのATMにそんな機能が付いているのを、僕は見たことがありません。そもそも通帳なんてあるのか?
しかし今、日本でも現金から電子マネーへのシフトが進んでいます。海外でも、さすがにビットコインは限定的でしょうが、ウォレットアプリは常識ですね
つまり、日本のATMがほこる通帳繰越の、至れり尽くせりの技術は、世界的には必要とされていない
タクシーもそうでしょう。東南アジアでは、「Grab」アプリなしでは、場合によっては命に関わります
ロックダウンが解除されたフィリピンは今、コロナの影響による経済難で、治安レベルがかなり悪いといわれています。日本人で、流しのタクシーに乗る勇気がある人は…命を大切にとしか言いようがない、言い過ぎでしょうか苦笑
片や、日本では、規制が厳しくGrabが参入できません。Grabに出資しているソフトバンクの孫社長が、かつて日本の規制を嘆いていました

世界で感染拡大を続けたコロナウイルスが、「ひとつ飛び」リープフロッグをさらに加速させた感があります
コロナ禍で、日本に限らずですが、百貨店など対面接客型の販売形態が、ことごとく不調に陥りました
代わりにシェアを伸ばしたのが、AMAZONや楽天などの、ネット通販であり、Netflixなどのサブスクでした
飲食店も、いうまでもありませんね
Uber Eatsは、もはや有力な、食事の選択肢です
海外でも事情は似たり寄ったりでしょう
かつて、発展途上国での宅配は、配達先までの「ラスト・ワンマイル」がネックになって物流の発達が進まないとも言われてきました
しかし、それもコロナ禍で大きく変わりました
日本人が、いまだに「当たり前」と思っていることが、実は海外ではすでに「時代遅れ」ということが、意外と多い気がします
海外は一周遅れだと思っていたのに、実は先を走っていた
ずるいじゃないか
そんなことを言っても、まったく意味がないですね苦笑
新しいものを貪欲に取り込もうとする海外の人々
一方で、新しい案件を通すのに、「社内稟議」を作り、多くの役職者の「おじぎハンコ」をもらって、あっという間に1ヶ月、とか笑
そんな国に生きている我々に、彼らのような「貪欲さ」はあるでしょうか?
大切に守ってきたものが、実はもはや「ただのガラクタ」でしかなかった。そのようなことは、避けて生きていきたいですよね